戻る
このページは以下URLのキャッシュです
http://famicoroti.blog81.fc2.com/blog-entry-2505.html
|
幻の発売中止SFCソフト『サウンドファンタジー』をめぐる物語 (3/3)
<現存する「サウンドファンタジー」完成版>
2010年8月――
原宿VACANTにて「横井軍平展 -ゲームの神様と呼ばれた男-」が開催された。そこにはメディアアーティストとして表舞台から姿を消していた岩井敏雄(敬称略)の姿があった。トークショーの出演が目的だったことが、自身のブログに言及されている。(※出典)
そこで彼は、かつて横井軍平(敬称略)とともに開発していた幻のSFCソフト『サウンドファンタジー』のパッケージや説明書などを披露。開発ROMを持参して実際にプレイして見せた。
その様子がこちらである。
この開発ROMが最終版と見て間違いないだろう。
1999年に放送されたNHK『課外授業 ようこそ先輩』に出演したときも、彼はこの開発ROMを持ち込み、生徒たちに『サウンドファンタジー』を遊ばせているシーンが確認されている。

※ 『岩井俊雄の仕事と周辺』(六曜社/2000) サウンドファンタジーより
また、2000年に発行された『岩井俊雄の仕事と周辺』にも、彼の所有している最終版開発ROMのものと思われる画像がいくつか掲載されていた。
<アート性が高い評されている作品たち>
結局のことろ、ふたりの天才をもってしても、ゲーム性とアート性が奏でるハーモニーは不協和音に終わったわけだが、それはあまりにも早すぎる挑戦だった故か、それともただのアイデア倒れだったのか……
ひとつだけ確実なことが言えるとしたら、『サウンドファンタジー』の不発以降、次世代を象徴するゲーム機の登場によってゲーム性とアート性の両立を果たしたような奇作・怪作・傑作が、次々と世に放たれるようになったということだ。
『サウンドファンタジー』の位置づけを見定める上で、そういった流れも押さえておくに越したことはないだろう。以下、マルチメディア時代にリリースされた「アート性が高い」と評されている作品たちを見て行くことにする。
これらの作品の多くは「ゲーム性とアート性の融合」を目指していたというよりも、マルチメディア時代がもたらした様々な可能性を、ゲーム的なアプローチによって実現させたことによって、結果的にゲーム性とアート性が融合しているように見える作品と表現したほうが近いと思われる。
その点があくまでメディアアート的アプローチにこだわった岩井作品との違いである。
※ もちろん『サウンドファンタジー』とこれらの作品とでは、そもそもコンセプトが違うということは承知の上で比較している。
<ゲーム性とアート性は両立するのか?>
最後に、メディアアーティスト岩井俊雄が満を持して世に送り出した『エレクトロプランクトン』の内容から推測する『サウンドファンタジー』発売中止の原因と、ゲーム性とアート性の両立について指摘しておきたい。
動画を見てもわかる通り『サウンドファンタジー』の面影はないが、むしろ、没入性の高いハンドヘルド型、そして直感的な操作が容易なタッチペン入力というDSの強みが、岩井の目指すメディアアート作品の方向性と非常にマッチしており、彼の実現したかったことを、SFC時代よりも数段高い次元へ昇華させた作品のようにも見える。
そう考えると、『サウンドファンタジー』が発売中止となった原因は、早すぎたのではなく、単純にSFCとの相性が悪かっただけのように思えるのだ。
ただし芸術性が高い作品が、必ずしも商業的に成功するわけではない。『エレクトロプランクトン』もまた、その完成度のわりにヒットしたとは言いがたい作品だった。
それはビデオゲーム以前から存在した映画・漫画・アニメといったメディア作品が通って来た道でなのかもしれない。『Rez』の寸評の中でも少し述べたが、ことさらゲームに対する「芸術的」という評価は、前衛的すぎる作品、あるいは、商業的に失敗した作品に対するエクスキューズ的な意味合いで使用されることが多かったため、ほとんどのゲームクリエイターはこの言葉を歓迎していないのだ。故に、彼らはゲーム的アプローチに固執しているとも言えるであろう。
あるいは盲信しているのかもしれない。なぜなら我々も信じているのだ。その異常なまでの全能性と、とてつもない発展力でもって、ゲームは簡単にアートを飲み込むことができるということを。しかしそれはアートも同じことだ。アートもまた、簡単にゲームを飲み込むことができるくらい異常なまでに「何でもあり」で、とてつもない勢いであらゆるものを内包して来た。
つまり、両者は最初から融合などしないのだ。両立などありえない。そこには、どちらかがどちらかを飲み込むことでしかお互いの存在を認め合えないという排他律しかないからだ。そう考えると『サウンドファンタジー』もゲームの土俵に立っていた時点でゲームでしかなかった。かつ、それで十分だったのだ。任天堂が求めたものは「そういうこと」だったのではあるまいか……
いずれにせよ『サウンドファンタジー』はゲーム史の徒花などではない。それはゲームとアートの排他律という難敵に挑んだ、一人のメディアアーティストの戦いの記録である。我々はこの貴重な「枯れた技術」がいつまでも保存
- 関連記事
-
- 押し入れから出てきたスーファミを息子にやらせてみた結果……
- SFC新作『ザ・ダークネス・ハンター -UNHOLY NIGHT- 魔界狩人』内容・評価・価格まとめ
- SFCクイズゲーム致命的ミスに苦しい注意書きが話題(しかも裏話有)
- 『スト2』ターボのポスターが10万円を超える事案が発生 他
- スーパーファミコンのカセットが“半分だけ”変色する謎
- スーパーファミコン「プレミアソフト人気ランキング31本」 2017年版
- UE4で製作された『スーパーマリオ64』の出来が良過ぎると話題
- スーパーファミコン内蔵テレビの展示品が高額で落札される!!
- 2017年3月30日発売 SFC新作『Unholy Night 魔界狩人』予約開始!!
- 幻の発売中止SFCソフト『サウンドファンタジー』をめぐる物語 (2/3)
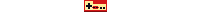
コメントの投稿
このブログについて
プロフィール
月別アーカイブ
- 2017年 06月(36)
- 2017年 05月(39)
- 2017年 04月(32)
- 2017年 03月(23)
- 2017年 02月(16)
- 2017年 01月(20)
- 2016年 12月(36)
- 2016年 11月(40)
- 2016年 10月(28)
- 2016年 09月(26)
- 2016年 08月(24)
- 2016年 07月(17)
- 2016年 06月(25)
- 2016年 05月(26)
- 2016年 04月(24)
- 2016年 03月(24)
- 2016年 02月(22)
- 2016年 01月(15)
- 2015年 12月(17)
- 2015年 11月(24)
- 2015年 10月(29)
- 2015年 09月(21)
- 2015年 08月(9)
- 2015年 07月(33)
- 2015年 06月(41)
- 2015年 05月(30)
- 2015年 04月(21)
- 2015年 03月(30)
- 2015年 02月(32)
- 2015年 01月(22)
- 2014年 12月(18)
- 2014年 11月(19)
- 2014年 10月(11)
- 2014年 09月(16)
- 2014年 08月(27)
- 2014年 07月(16)
- 2014年 06月(27)
- 2014年 05月(23)
- 2014年 04月(34)
- 2014年 03月(13)
- 2014年 02月(7)
- 2014年 01月(10)
- 2013年 12月(9)
- 2013年 11月(8)
- 2013年 10月(11)
- 2013年 09月(16)
- 2013年 08月(22)
- 2013年 07月(26)
- 2013年 06月(28)
- 2013年 05月(30)
- 2013年 04月(24)
- 2013年 03月(33)
- 2013年 02月(30)
- 2013年 01月(27)
- 2012年 12月(18)
- 2012年 11月(29)
- 2012年 10月(36)
- 2012年 09月(29)
- 2012年 08月(33)
- 2012年 07月(42)
- 2012年 06月(31)
- 2012年 05月(24)
- 2012年 04月(21)
- 2012年 03月(20)
- 2012年 02月(28)
- 2012年 01月(13)
- 2011年 12月(18)
- 2011年 11月(20)
- 2011年 10月(13)
- 2011年 09月(20)
- 2011年 08月(21)
- 2011年 07月(20)
- 2011年 06月(23)
- 2011年 05月(16)
- 2011年 04月(20)
- 2011年 03月(15)
- 2011年 02月(11)
- 2011年 01月(9)
- 2010年 12月(19)
- 2010年 11月(13)
- 2010年 10月(12)
- 2010年 09月(13)
- 2010年 08月(19)
- 2010年 07月(5)
- 2010年 06月(5)
- 2010年 05月(9)
- 2010年 04月(7)
- 2010年 03月(8)
- 2010年 02月(7)
- 2010年 01月(9)
- 2009年 12月(6)
- 2009年 11月(9)
- 2009年 10月(10)
- 2009年 09月(7)
- 2009年 08月(6)
- 2009年 07月(10)
- 2009年 06月(9)
- 2009年 05月(6)
- 2009年 04月(4
過去の記事
(ランダム表示)
(ランダム表示)
Powered by 複眼RSS
ニュースサイト
相互リンクサイト
お知らせ
| オロチの小説。 カクヨムにて公開中! |
QRコード

スポンサー
最近の人気記事ランキング
カウンター
お勧め記事
・スーパーマリオの左右論(1) インターフェイス由来説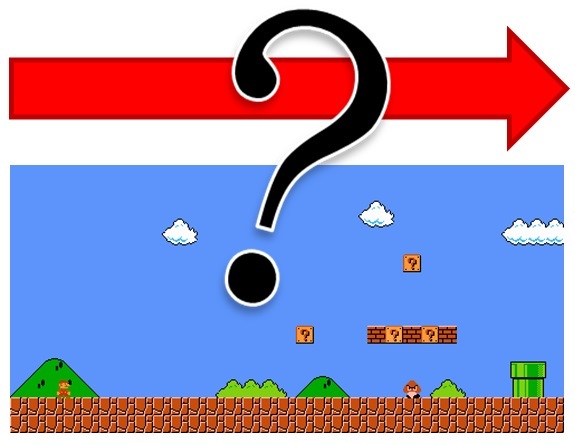 なぜマリオは左へ進むのか。インターフェイス・言語・科学・物語のロジック。様々なアプローチからその謎を追及する!! |
・なぜスマホゲームは「時間の無駄」なのか? スマホゲームとその他の趣味・娯楽の圧倒的違いとは何か。オロチ独自の視点から分析した記事。 |
・“懐かしい”という感情の正体について 再考 おそらく人間だけが持っているだろう“懐かしい”という感情の正体に迫る。完結編。 |
・愛知県でレトロゲームが買える店 2017 随時更新&随時情報募集中!! |
カテゴリー
- ファミコンネタ・コラム (136)
- ファミコンニュース (236)
- ゲームネタ(全般) (14)
- 気になるファミコンのネタ!! (664)
- リメイク・新作 (70)
- オークション お宝・非売品 (94)
- オークション おもしろ・珍品 (70)
- オークション 話題・その他 (49)
- ファミコントリビア (47)
- ファミコンサイト (42)
- ファミコン動画 (77)
- ファミコン動画 TAS系 (15)
- ファミコン書籍・アイテム (83)
- 画像・アート・ファッション (100)
- オリジナル・改造・ハック (42)
- ファミコン音楽・演奏 (39)
- 任天堂 (50)
- SFC・64 (25)
- ゲームボーイ系 (14)
- NES(海外ファミコン) (21)
- 高橋名人 (31)
- SEGA系 (18)
- ゲーム業界 (43)
- レトロゲーム (82)
- レトロPC・レトロ家電 (4)
- レトロアーケードゲーム (9)
- ロードランナー自作面 (18)
- マイティ文珍ジャック (4)
- あのファミコンメーカーは今!? (10)
- オロチのファミコン収集記 (16)
- 女の子にウケるファミコンソフト (5)
- このブログについて (1)
- まとめ (22)
- 思い出・プライベート (37)
- PS1・SS (1)
- レトロ玩具・グッズ (5)
- アーケード筐体救出プロジェクト (4)
最近の記事
最近のコメント
- 名無しさん@ニュース2ちゃん:「思い出補正」って言葉が釈然としない理由 (06/29)
- 名無しさん:PCエンジン幻級ソフト『ハドソンコンピュータデザイナーズスクール卒業記念アルバム』の最終号が発掘される!! (06/29)
- eagle0wl:PCエンジン幻級ソフト『ハドソンコンピュータデザイナーズスクール卒業記念アルバム』の最終号が発掘される!! (06/29)
- 名無しさん:PCエンジン幻級ソフト『ハドソンコンピュータデザイナーズスクール卒業記念アルバム』の最終号が発掘される!! (06/29)
- 名無しさん:10月5日ついに発売!! 「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」収録は21タイトル (06/29)
- オロチ:PCエンジン幻級ソフト『ハドソンコンピュータデザイナーズスクール卒業記念アルバム』の最終号が発掘される!! (06/29)
- ファミコン現役:10月5日ついに発売!! 「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」収録は21タイトル (06/28)
- 名無しさん:10月5日ついに発売!! 「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」収録は21タイトル (06/28)
- 名無しさん:PCエンジン幻級ソフト『ハドソンコンピュータデザイナーズスクール卒業記念アルバム』の最終号が発掘される!! (06/28)
- オロチ:ヤフオク!毎日くじで1等を当てたら地獄の1日が始まった話 (06/27)
全記事表示リンク
逆アクセスランキング
リスペクトサイト
レトロゲーム関係ブログRSS
カウンター






