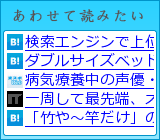その10年後に絶望して完全引退するまでの話
全てが終わってかなり経ったから書く
どこかに10年間の記録を残しておきたいから書く
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1537880566/
当時2000年代後半、ラノベ業界は急速に活気づき始めていた。
ハルヒのアニメ化一期が大成功し新レーベルが次々と参入し、
その知名度と市場は一気に膨れ上がっていった。
それまでのラノベと言えばシャナかブギーポップあたりが少し話題になっているくらい。
それもあくまで「シャナ」「ブギーポップ」という個別の作品が売れているだけであり、
ラノベというジャンルはまだまだ一般的にも(ネットにおいても)認知されていなかった。
今となっては信じられないかもしれないが、ネットとラノベはとても遠い存在だった。
電撃の新人賞受賞者があとがきに2ちゃんの有名コピペを仕込めば、それだけでネットは大喜びだった。
あとがき横読みで出る「どう見ても精子です。本当にありがとうございました」で2ちゃんは盛り上がった。
今よくある炎上系批判の盛り上がりではなく好意的な盛り上がり、
それこそ「ラノベ作家が2ちゃん見てた! このカキコも見てる?」のような喜びの祭りが開催された。
当時ツイッターなどは勿論なく、ただ作者への一方通行だった。
ラノベ作者が見ているに違いないと信じて書き込む、ただそれだけの遊び。それでみんな楽しんでいた。
それは「オレら2ちゃんねらーの力でハレハレユカイを一位にしようぜ祭り」
アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の主題歌である「ハレハレユカイ」。
それを2ちゃんで宣伝して皆で買いまくってオリコン一位にしちゃおうぜ! という祭り。
オリコンにアニメソングなんて普通はあり得ない。
オレらの悪戯でそこにハレハレユカイをねじ込んで世間を驚かせようぜ! ……という祭り。
当時のネット(2ちゃん)民達は、どこからか来たこの祭りでそのまま素直に盛り上がった
ハルヒやみくる、長門といったキャラクター達のAAがどこからともなく作られてきて
それが各板で「ハレハレユカイを買おうぜ!」と次々と有志の手でコピペされていった
ハルヒのアニメ化は大成功した。
ステマなんて単語・概念が初めて出たのはこの五年以上も先の話だ。
ともかく当時はそんな感じの世界でありネット文化だった。
そのおかげかどうかはわからないが、ラノベ市場は一気に知名度と市場が膨大した。
初めの話に戻る。
2000年後半、次々と新しいレーベルがラノベ市場に参入していった。
参入出版社が増え出版数が増えれば、当然そこで書く者達が必要になってくる。
ラノベ作家需要の突然の高まりに次々と新人賞が創設され、また賞一回ごとのデビュー枠も激増した。
毎月というレベルで多量の新人が次々と受賞し、そして次々とデビューしていった。
発見された未踏の新大陸、果ても見えない広大な開拓地。そこに上陸した何十人のルーキー達。
その一人が俺だ。十数年前の俺は、そんな風にしてラノベ作家になった。
小学校の時に国語の授業であった「地図を見て物語を書いてみよう」で「作家になりたい」と思い、
そして中学の時にスレイヤーズにハマってラノベ作家志望になり、
そのまま十五年近くそのままラノベ作家になりたくて足掻いていた。
2ちゃんと出会ってからライトノベル板(ラ板)に入り浸り、お気に入りは新人賞スレだった
まだ「小説家になろう」等は存在せず、ラノベ作家志望はつまり新人賞への挑戦だった
新人賞スレはそんな者達が日々書き込みをし、ワナビと自称していた。
俺の仕事は実家自営業の従業員。父親が社長である零細自営の後継ぎ若造だ。
中学の時にラノベ作家を志望したガキは大学を出て親の会社に入り、そしてまだラノベ作家志望だった。
そんな二十代後半だったが、しかしこれでも当時のラ板ワナビの中では最年長な方だった。
スレの連中がルナ・ヴァルガーを全く知らない事に驚愕し、自分を年寄りだと思っていた。
年寄りなりに、婚約者がいた。といっても恋愛ではなく、会社の紹介で知り合った人だ。
とりあえず紹介されて何度か会って、まあ互いに他の相手もいないし結婚するんだろうな……という感じ。
具体的な話はこれからとして、とりあえず週に一度くらい会おうか。そんな感じ。
ワナビ十五年生の俺は、ほぼ第一期の新大陸開拓民としてラノベ作家になった。
俺の十年間は、そこから始まった。
今さらだが、この文章はすべて「俺」の記憶と認識によって執筆されることになる。
当時の日記などを参照してなるべく正確を心がけるつもりだが、
多分事実とは異なる個所や認識を争う箇所も出てくると思う。それはそういうものだとして読んで欲しい。
ハレハレユカイ一位祭りも、ひょっとしたら本当にただの純粋な楽しい祭りだったのかもしれないのだから。
また、ここで言っておくが俺は自分の筆名を明かすつもりはない。
この文章全体にいくつか、少しだけ小さな嘘を混ぜ込んである。いわゆるフェイクだ。
といっても『「少しだけの小さな嘘」という言葉が嘘であり全てが大きな嘘』とか
または『受賞したという事が嘘でありつまりこの全てが嘘』のような根底を覆すオチはない。
今更ここで文章解釈トンチ合戦をするつもりはないし、全く嘘の文書をここまで書く意欲ももうない。
(もちろん、『以上四行が嘘』という展開もない。そういう面倒くさい事はしない)
発売日が冬だったのを春としているとか、九巻完結であったのを八巻完結と書いているだとかその程度の嘘だ。
大勢や文脈に影響はないので、気にしないでほしい。
あと、蛇足になるが一応。
この文章の全ては俺の記憶と記録による文章であり、俺の自己正当化が多分に含まれている事になるだろう。
さらにそれを加味しても、以下の文章で俺はラノベ世界にかなり無礼な事をやっているし思っている。
まず初めにそれを許容しておいてほしい。
○プロ一年目。俺はラノベ作家になった。
授賞式は別世界のようだった。昔から身近に読んできたライトノベル、その「作者」が大量に目前にいた。
繰り返しになるが当時はネットとラノベは遠く、個人発信と言えば各人のホームページの「日記」くらい。
それも今ほど詳細に書く人は稀で、例えばシリーズ完結したとか大病したとかその程度の報告だった。
(新刊発売をネットで宣伝という概念はまだなかった。あくまでもファンに向けた「報告」だった)
読者にとってラノベ作家は遠い存在で、彼らが何を考えどんな生活をしているのかほぼ窺い知れなかった。
人間となって目の前にいる「作家」。知っている作品たちの執筆主と話すのは物凄く奇妙で凄い体験だった。
全員が同じ夢に向かってきていて、そしてここにいる皆は選抜された到達者なのだ。まあ仲良くもなる。
仲良くと言ってもミクシー公開繋がり程度の関係だったが、それでも仲良くなった。
皆が「レーベルを盛り上げる」という志を共にする仲間だった。少なくとも俺はそう思っていた。
厳密に言えば全員が零細個人事業主でありつまり同期は競合他社なのだが、
少なくとも俺は彼らをライバルと思った事はあるが敵と思ったことはない。
それは俺自身の性格が甘いからというのも勿論あるが、市場のおかげもあった。
当時のラノベ市場は、新人賞受賞作品はほぼ例外なくかなり売れたのだ。
当時は「新人賞受賞作、デビュー作」と帯を巻きさえすれば、それだけで売れた。
考えてみれば奇妙な話だ。何者なのかどんな作風かもわからない新人の作品がなぜそんなに売れるのか。
それは分からない。当時の俺は「そういうものだ」とだけ理解していた。現在の俺にも分からない。
分析すれば何らかの推測はできるのかもしれないが、俺には正確な分析を出来る情報はなかった。今もない。
ただ当時俺が感じていた事実を書いていく。これからもそんな感じでこの記録は進める。
勿論比較的売れない新人もいて、そういう作品は『たったの三・四巻で』打ち切りされたりもしていたが、
その新人たちも第二シリーズをほぼ約束されていた。その第二シリーズが爆発的に売れる例もあった。
受賞シリーズでぱっとしなかった者が敏腕編集に助言されて次は大ヒット。そんな話もよく聞いた。
つまり、俺達は「仲間同士」で争う必要なんか全くなかったのだ。
採掘場を取り合うヒマがあるのなら、新しい鉱山を探せばいい。開拓地はまだまだ広いのだから。
俺はそう思っていた。多分、皆もそう思っていた。
正確には「思っていた」んじゃない。
現実がそれでそれ以外の世界なんか存在しないのだから、思うとか考えるとかする必要もなかった。
未来には想像もつかない世界があるなんて、だれも予め想像しやしないのだ。
というより、かなり売れた。俺のデビュー作は相当に売れた。
当時、「大阪屋」というランキングがあった。とある卸問屋のランキング……だったと思う。
詳しいシステムは分からないが、それである程度の売り上げが分かった。月曜日が更新日だった。
勿論完璧に正確なランキングではなくあくまで一つの参考ランキングに過ぎなかったが
他に参照する物はあまりなく、特にネットにおいては適当な売り上げ指標として順位が書き込まれていた。
2ちゃんではそれがどこまで正確かでいつも揉めていたが、少なくとも俺は非常に参考にしていた。
俺のデビュー作は他の同期をぶち抜き、レーベル主力のベテランにすら届きかねない勢いで売れた。
「ガンガン行きましょうどんどん書いてください」という言葉を担当編集に貰った。
俺は出版された本と契約書を見せて、父親=社長と交渉する事にした。
今後、本業の傍ら兼業ラノベ作家として本を出版していく事を許可してほしい……と。
交渉は成功した。父は俺がプロ作家になるのを歓迎してくれた。
社長は俺の兼業を許可し、更に本業に支障が出ない限り自由に有給を取っていい事になった。
それははっきり言って、天国だった。喜びと興奮と快感ばかりだった。
そもそも俺の待遇は土日祝完全休日で、勤務時間は朝の八時から夕方の五時だった。
自主的な勉強や資格修得や残業をしない限り、それはそれとして日々が平穏に過ぎていく環境だったのだ。
そこに、更に40日の有給を自由に使える事になった。体感的にはいつでもいくらでも休めた。
還暦とはいえ父はまだまだ健康で、母も変わらず元気だった。家の事は何の手間も憂いもなかった。
月に最低でも一回、普通なら二回、多い時は三回も泊りがけで出かけた。
打ち合わせと称して、執筆缶詰と称して、取材と称して、または本当に単なる遊びで。色々な所へ行った。
コミケにも行った。五泊六日くらいの日程で、挿絵のイラストレーターに片っ端から挨拶した。
上京からの帰りには欠かさずどこかの観光地に寄った。缶詰の温泉旅館も金額を選ばなかった。
あるいはごく普通の平日に突然一日休んでひたすら執筆をした。
いつ休んでもいい。仕事は適当にすればいい。ただ執筆していればいい。それで続刊が続々と出版される。
小学校卒業文集に「作家になりたい」と書いた。中学生では自作の表紙を夢想していた。
高校の時に密かに作品設定を練り、大学生になって文芸部の友人とともに投稿を始めた。
社会人になってもまだ諦めきれなかった。十八年間も夢見ていた。
いつかラノベ作家になりたかった。でも夢だった。「宝くじで十億円当たったら」とか、そのジャンルの夢だ。
しかしその夢が今、本当に実現しているのだ。本当に現実に、俺はラノベ作家だ!
結果は次々と出せた。三巻を数えた時点で2ちゃんねるに専用スレが立った。住人は好意的だった。
四巻の発売日、ふと思い立って日本縦断旅行をした。北海道から沖縄まで本屋を巡り自作の存在を確認した。
貯めてあった40日の有給をどんどん使い、更に年度替りで20日弱の有給追加があった。
まだまだいくらでも休めて、どこにでも行けて、何でもできる。俺は自由で無敵だった。
狂乱の中でプロ作家生活は二年目を迎え、俺は三十歳になった。
でも連投対策(あるのかどうか知らないけど)でたまに助けてくれると嬉しい
○プロ二年目。俺は有頂天だった。
次の受賞作が発表され、二回目の授賞式に行った。後輩が出来た。それとも仲良くなった。
友人がだいぶ増えた。連絡を取り合える仲間がだいぶ増えた。殆どが年下だった。
殆ど二十代の前半か十代の後半で、中には学生もいた。俺のような年代は珍しかった。
皆で、この世界を変える話をした。実際に世界は変わったのだ。俺たちの手で。
本屋のポスター、レーベルのチラシ、出版社の公式ホームページ、販売予定表、そして平積みの新刊。
「ラノベ業界」という俺達の世界。その世界の形を、俺達は作る事ができた。変える事が出来た。
十五年間のワナビ生活においては、世界は俺の手が届く範囲しか変えられなかった。
大学の時に作った合同誌は俺が刷った数しか存在しなかったし、俺が置いた場所にしか存在しなかった。
だが今は、俺の本が日本中に存在する。あの山の向こうの町にも、あの海の向こうの島にも。
授賞式からの帰り、ふと田舎の駅に降りてみる。その町の本屋にも俺の本は並んでいた。
俺が世界のシステムに直接干渉し、世界の景色を変える。そんな実感だった。
俺は……俺のシリーズは、その後輩の新人デビュー作にすら勝った。
実際それは大健闘だった。新人受賞作は変わらず売れた。俺の本はそれより売れたのだ。
CDドラマの話が出てきた。ある日の打ち合わせで、担当が雑談の中で漏らした。
CDドラマ、つまり声がつく。俺の作ったキャラ達を演じる声優が決定される。
つまりそれは、アニメ化の準備か予行演習のようなものだ。俺はそう理解した。
アニメ化が射程に入った。あとは書くだけ。ただ書けばそれで全てが付いてくる。人生の全てが。
人生の全ては、ここにある。この先にある。そう信じていた。
青春だった。三十路を越えた身だったが、それは紛れもなく俺の青春だった。
夢想し始めてから十八年。目指し始めてから十五年。長かった。長い幼年期、長い準備期間だった。
それがやっと終わった。準備ができた。成長できた。そして俺は青春に到達したんだ。そう信じていた。
青春だった。全ては右肩上がりで無敵で永遠だと、疑いもなく信じていた。
俺は受賞した直後にワナビスレに書きこむのを止め、以後は閲覧のみという事にした。
そしてプロスレへと移動した。当時は創作文芸板にあった「プロ作家のための愚痴スレ」。
当時そこにあったのは、愚痴とは名ばかりの自慢、選ばれた自覚者達の謙遜だった。俺もそうだった。
大量に発生した新人ラノベ作家は、そのままプロスレにも大挙して乗り込んでいたのだ。
「編集からの返事おっそ! 再来月発売なのにヤッベ!」のような、余裕に満ちた自慢があふれていた。
この頃から他の板にも「ラノベ作家だけど質問ある?」みたいな勢い余ったスレが立ち始めるようになった。
疑いようもない。あのスレの誰かが立てたのだ。俺ではないけど、「俺たち」のうちの誰かが。
なんなら、俺がそのスレを立てていても良かったんだ。先を越された。内容なんて同じなんだから。
業界の未来の事は考えていたけど、自分の将来の事なんか誰も考えていなかった。
業界すら若かった。なにしろ、レーベル新人大量拡大期からまだ数年も経っていない。
市場がいきなり拡大して、世界が変わって、そして俺たちがその第一期だった。
先輩はいなかった。先を行ってその景色を若者に報告する者はいなかった。
勿論、当時この時にもベテランと呼ばれるプロはいた。でも彼らは少数で、そして寡黙だった。
将来の不安なんて、ただ一言で吹き飛んだ。「でもとにかく、売れさえすればいいんだろ?」の一言。
そう、とにかく売れさえすればいい。どんどん売れてアニメ化でもすれば全て解決だ。
今のシリーズが、または次のシリーズが一気に売れさえすればいい。たったそれだけで解決だ。
それで一気に大金と名声を稼いで、あとは悠々と人生逃げ切り。俺には、俺らにはその力がある筈だ。
こんな天才がデビュー、次はこんな変わり種がデビュー。なんと同時受賞。次々と景気のいい話が出てきた。
「来月のラノベ新刊」として、華々しく並べられた萌え系表紙(エロゲー絵師が殆どだった)。
それらを見て、ネットの人々は「こんなのが売れるだなんて、いよいよジュヴナイルも終わりだ」等と嘆き、
または「これのどれかはアニメ化してしまうんだろう。出版社もプライドがなくなった」等と揶揄した。
皆、「売れる」事を疑わなかった。こんなものが売れてしまう。売れるだろう。
どれもそこそこは巻数が出て、そして当然アニメ化されるのだろうと、嘆き呆れながらも認めていた。
意味に違いはあれ、ネット民ですら新人達の未来を信じていた。
読者も、ラノベに纏わるネットすら若かったのだと思う。
未来の先と限界を想像せずに、ただ明るい将来だけを信じていた。
少し考えればわかる筈の必然未来、数年後にやってくるのが明らかな物理限界の事を、誰も考えなかった。
CDドラマとアニメ化の話は、結局他へ行ってしまった。
ベテランがシリーズを始め、それが圧倒的に売れてそっちへ行ってしまった。
アニメ化の候補からも外れてしまったのだろう。
という訳で、俺の第一シリーズはそろそろ終わろうかという話になった。
ここらで心機一転、第二シリーズでアニメ化を目指そう。担当はそう言った。
俺は第一シリーズの終了を宣言されつつ、しかしそんなにショックは受けていなかった。
「まあ、これがプロの世界だからな」と嘯く余裕すらあった。
正直、内容的にはここら辺で畳んでしまうのがベストだと思っていたのだ。
アニメ化となれば更に続刊を次々に出す必要があるだろう。それは難しいかもしれないと思っていた。
結局、あと二冊で終わりという事になった。
終わって、そして即座に第二シリーズに取りかかろうという事になった。
俺はその件を婚約者に伝えた。
婚約者の返事は、「もうあなたとは結婚できない。もう会いたくない」だった。
俺は受賞以来、婚約者に殆ど時間を取らなかった。全ての休日は執筆と外出にあてた。
結婚やその後の生活を考えるより、執筆と出版の方が圧倒的に面白かった。
ラノベは俺の生活の全てて、その「全て」には、婚約者の事は全く含まれていなかった。
それでも第一シリーズ完結まではどうにか待った。でも更に次も始めるという。もう無理。
言われてみれば納得だ。俺は、完全に振られた。
こちらは、流石にショックだった。別れを告げられた帰り道の事は未だに覚えている。
――しかし。三十路にして破局した独身男は、しかし、すぐに持ち直した。
そう、これで『結婚しなくてもよくなった』のだ。限りある時間を意識する必要はなくなった。
婚約者としての責任とか流石に具体的な話をとか、そういう事を気にする必要が全くなくなったのだ。
なにしろ、向こうから別れ話をしてきた。これはもうどうしようもない。結婚できない。しなくていい。
あとは数カ月に一度くらい見合いなり何なりをしてるフリでもしておけば、それだけで面目が立つ。
今のなろう需要みたいなもん
ラノベは一時期100人くらい毎年デビューしてたからね
しかも一般文芸の新人賞獲った人達より待遇が良かったし
一時期は一般で書いてる連中がラノベそんなにデビューし易かったら
ラノベから作品出した方がいいんじゃね?みたいな話よくしてたし
ほんの数人の例外を除き、金持ちである筈のベテラン売れっ子ですら結婚していない。
ラノベ作家は殆ど結婚しない。そして、俺はラノベ作家なんだから結婚しなくていい。
結婚さえしなければ、まだまだ旅行にも行ける。次の、更にずっと先のコミケにだって行ける。
何より、執筆に集中できる。第二シリーズを全力で書く事が出来る。
俺はこの時、全力でラノベ作家だった。それ以外の事を捨てて平気でいられる程度に。
元婚約者との別れは、揉めることもなくごく順調に終わった。
元婚約者の「もう会いたくない」の手紙に俺は「そうしましょう」と返し、それで全て終わった。
それだけで済ませ、俺はシリーズ最終巻を書きあげた。初のシリーズを完結させた。
最終巻の発売日、俺は秋葉原にいた。秋葉原のアニメイトで完結巻の店頭発売を確認した。
忘れもしない。シリーズ一冊目、最初のデビュー作を本屋で確認した最初の本屋。
その同じ場所で、シリーズ最終巻の発売を確認した。これまでの既刊が平積みにされているのを確認した。
秋葉原のアニメイト、そのラノベコーナーの一角の本棚。そこで、俺は泣いた。
オタ店のラノベの棚で一人泣く三十路男。それはどう見ても不審者だっただろう。
今後また途切れるかもしれんけどまたすぐどこかで続きは書く
当日秋葉原にいた理由……上京していた理由は、第二シリーズの企画打ち合わせだった。
第二シリーズ打ち合わせは、最終巻の校正を渡したその日から始まっていた。
それは俺の「次は『ゼロの使い魔』みたいな異世界ワープものにしたいんですけど」という提案から始まった。
担当は即座に「異世界ワープ? そんなのより学園で変な部活とかそういうのでいこうよ」と返事した。
俺は「そうですね。異世界ワープなんて古いし、今の子には売れないですよね」と納得し、提案を取り下げた。
「異世界ワープなんて売れない」というのが当時の「市場分析」だった。
「今どきの子は学園と家とコンビニしかないから異世界なんて面倒くさがる」というのが「読者分析」だった。
俺の異世界ワープ企画提案も、正直本気ではなかった。
「まあ冗談はこれくらいにしまして」みたいな、最初の挨拶代わりの提案だった。
当時ちょうど「俺の妹がこんなに可愛い訳がない」が大ヒットし、続刊を重ねていた。
俺はその製作秘話インタビューをレーベルのホームページで確認していた。
『担当が作家に漫画「GTO」の全巻を読ませ、それを元にヒロインを作らせた』という話が載っていた。
俺はその逸話を聞いて、大いに感心した。流石に一流の編集者は目の付け所が違う。と感心した。
GTOヒロインがなんでラノベで売れたのか俺には分からないが、編集者にはわかるのだろう。
俺も頑張ろう。俺の担当はその人ではないが同業だ。似た能力を持っているはずだ。その時はそう思った。
根底の事はすぐに決まった。『学園モノ、部活、オタク、ちょっと異能』。
中高生はそういうのが好きなんだから、これさえ押さえておけば安心。いわゆる『鉄板』だ。
底面の鉄板はまず決定し、そして難航が始まった。
第二シリーズの企画は、難航していた。
第一シリーズの最終巻発売日になっても、まだ方針すら固まっていなかった。
担当は「主人公とヒロインが殺しあう話」をひたすら推してきた。
俺は担当の言葉を聞きつつ、しかし意味がさっぱりわからなかった。
高校生が校舎内で殺しあう? それで普通に授業するの? 警察は? 部活も一緒? そしてラブコメ?
俺にとって「殺し合い」は互いに拳や刃物や拳銃を使っての憎悪のぶつけ合いであり、犯罪行為だった。
実際、第一シリーズ一巻はそんな感じだった。主人公が敵に殺意を向ける。殺しあう。敵は死ぬ。
それに対し担当の「殺し合い」は「異能高校生が互いに超必殺技を打ちあう」みたいな感じ……だったと思う。
その齟齬は頭では理解していた。そもそも高校生が拳で人を殺そうとする方がおかしい。超必殺技のが健全だ。
しかし俺には「殺しあいつつラブコメ」の企画は難しかった。
俺は「ライトノベルの企画打ち合わせ・会議」について、大いなる誤解をしていた。
作者が企画やアイデアを自由勝手に提出し、担当がそれを受け取って頑張って形にしていく物だと思っていた。
実際、今まではそういう作り方をしてきたのだ。俺の意見はほぼ通り、そしてそのまま形になっていった。
俺が「次はこんなヒロインを出したい」と言えば、担当は時に渋りつつも基本的に採用してくれた。
新刊でイラスト化した自分のキャラを見て、更に次の展開を夢想する。採用される。そんな方式だった。
しかしその状況は、ラノベ業界全般においては「たまたま発生していた稀少状態」に過ぎなかった。
「売れているシリーズの続刊だから」たまたまそうなっていたというだけの話だった。
現在進行形で売れているシリーズのその続刊は、内容より速度が重要だ。
揉めたり修正したりしている時間がもったいない。作家が書きたいと言えばとりあえず書かせ、出版する。
勿論あまりにもおかしな方向へ進んだら修正はするが、基本的に作家の書きたいように書かせる。
レーベルにもよるとは思うが、少なくとも俺の属していたレーベルはそうだった。
しかし今は、新シリーズ立ち上げは違う。速度より、内容。
時間経過はデメリットではない。多少遅くなってもいいのだ。
「売れているシリーズの作家」ではなくなり、「第二シリーズ企画中の作家」になった。
即ち、「最優先すべき作家」から、「後回しにしていい作家」に。
俺は売れっ子作家だった。若手の一番手で、全体でもエースと呼んでも差し支えない位置にいた。
故に、担当にとって俺は最優先だった。他の用事を止めてでも優先してくれた。
だが今は違う。「売れていたシリーズ」を終わらせた俺は、もうその立場ではなくなった。
他の「そこそこ売れている続刊」を持つ作家が最優先だ。俺は、その次。
担当にとって俺はもう最優先ではない。他の誰かが最優先。
俺を最優先してくれ、そして俺がその全てを依存していた相手が、他の者を優先し始めた。
それは一方的な恋愛関係に似ていたし、そしてその末の失恋にも近かった。
他のレーベルであるA社(頭文字ではない)に、企画を出した。
以前参加したとあるイベントで、A社の編集者の名刺を手に入れていた。それに連絡した。
いい感触だった。A社は俺の企画を褒めてくれ、出版への検討を約束してくれた。
浮気は順調に進み始め、そして俺はその後ろめたさを隠す為に担当に変わらず接した。
変わらずアイデアを練るフリをし、そして形だけの企画書を送った。
この時の企画は、今まで出してきたのに比べると相当に気が抜けた企画書だったと思う。
どうせこの企画もいつも通り没にされる。そしたら、いよいよA社の編集と会ってみよう。
そんな捨て駒、踏み台のような企画書を作って担当へと送った。
そしたら、その企画はあっさり通ってしまった。
気合も入れずに作った、とりあえず出しましたというアリバイのような企画。それが通ってしまった。
担当はその気の抜けた企画に突然「いいですね」と返事し、そして執筆が許可された。
なんでいきなり通ったのかは分からない。気を抜いた事がうまくいったのかもしれない。
それともひょっとして、担当がA社の動きを聞きつけ、引き留めるために通したのかもしれない。
真実は分からないが……とにかく、どうあれ、第二シリーズの企画は通ったのだ。
A社の編集とは結局会う機会が作れず、そして元の担当の下での執筆が始まった。
完結巻発売してかなり経ち、感想やレビューはもう出揃っていた。
どれもこれも、好意的だった。傑作と称してくれた人もいたし、作者を麒麟児だと呼んでくれた人もいた。
正直、自分で言うのも何だが第一シリーズは奇跡的によく出来た。理想的に進行し、完結した。
作者と作品と主人公が一緒に成長し、そして最終回へと到達する。全ての事が理想的に回った。
そして、第一シリーズでこういう執筆方法をすると第二シリーズが難しくなる。
作者は第一シリーズで成長しきった。第一シリーズの世界は成長し、完成した。
しかし、第二シリーズの主人公と作品は生まれたてだ。まだ何の物語も持っていない「これから」の存在。
つまり、作者が作品・主人公に対し「上から目線」「先達者の説教」になってしまう。
そして正直なところ、『気を抜いた企画』だった為、統合性がイマイチだった。
執筆は、少しだけ苦しかった。第一シリーズの時には無かった苦労があった。
ヒロインの性格も、企画の段階より多少変わってしまった。
とはいえ……とはいえ。しかしとにかく、第二シリーズの一巻は完成した。
第一シリーズ完結校正を渡してから数ヶ月経過、やっと第二シリーズ一巻の原稿が完成した。
担当は一巻の原稿を受け取り、そして会社の公式HPに「発売予定」が載った。
俺のスレには「待ってました」「ついに新シリーズ!」等の声が上がった。
もっとシンプルに済ませられんのか
年明け間もなく。第二シリーズの一巻発売日。俺はまた東京にいた。
既に二巻を書きあげ、その仕上げの打ち合わせのために上京していた。
二巻の完成原稿を前にして、担当は言った。
「一巻いよいよ発売ですね。これで二巻が出ないなんて事になったら、私は編集長に直談判しますよ」
俺はその言葉に大いに安心し……そして、違和感を覚えた。
『二巻が出なかったら編集長に直談判』……って。
『出なかったら』って何だ? 二巻って、確実に出るんじゃないのか?
ラノベ業界において『二巻』は、徐々に出にくくなっていた。
一巻が売れなければそれで終わり。二巻はない。そんな例が徐々に増え始めていた。
既に三年目の新人賞受賞者は発売されており、うち売れなかった受賞作もその一巻で完結してしまっていた。
新人賞を貰ったくせに売れないなんて、大失敗だったな。当時はそういう評価だった。
でもまあ……不安になりつつも、俺は一応安心していた。
何だかんだ言って、二巻はまあ出るだろう。秋葉原の本屋で一巻の平積みを確認しつつ、俺は安心していた。
こうして大々的に平積みされている。壁に貼られた「今月の新刊」のポスターでも、俺のが一番大きい。
前のシリーズは売れた。評判もいい。その第二シリーズだ。売れるはずだ。
編集長に直談判なんて選択肢なんか、そもそも存在しないだろう。
第二シリーズの一巻は、そこそこ売れた。
発売日の次の月曜日、一巻は大阪屋でそこそこの順位を出した。
二巻発売は確定し、そして三巻完結が宣告された。
「そこそこ」しか売れなかった。第一シリーズの時のようには売れなかった。
完結。つまり打ち切りだ。一巻発売から半月足らずで、それは決定してしまった。
二巻の原稿は既に完成し、そろそろ三巻を考えてみようかという状態で、完結が宣言された。
二巻はこのまま出すとして、三巻は完結を見越した物語にする事になった。
完結巻の打ち切り執筆は、しかしこれはこれで楽しかった。
考えていた・出したかったキャラを全て出し、最後に言いたかった事を全力で言って終わる。
既存のキャラはぶっ壊せばそれでギャグになって、そして完結なので何のあとくされもなかった。
俺は缶詰と称して連泊していた温泉宿で、完結巻を完成させた。
最近出来て、俺の知り合いの作家も参加しているというツイッター。以前から気になっていたのだ。
同レーベルの知り合いとも相互フォローし、そして連絡が日常的に頻繁にとれるようになった。
第二シリーズを終えた俺は、そろそろ授賞式以外で作家の知り合いと会う事を始めた。
ミクシィでは新人作家の集まりコミュができており、たまにオフ会をしていた。それに参加させてもらった。
集まりやイベントがあるたびに上京し、皆に会って名刺を配りまくった。色んなレーベルの色んな人に会えた。
ラノベ作家同士で秋葉原を巡るのは、なんとなく誇らしくて特別な視点に立った気がした。
店頭の巨大な看板を見て、すぐ横にいる作者に「製作秘話」を聞いたりした。
昔、新人賞の二次選考あたりで競い合った相手と再会? し、互いに当時の感想を言い合ったりした。
誰かがアニメ化すると聞けば皆で祝福したりした。カラオケも行った。10年ぶりくらいに歌った。
楽しかった。社会人になって初めて「友人」が出来た気がした。
受け取った契約書を確認する。数字を書いてしまうが、初版部数7400部。
7400部。二巻のほぼ半分。正直こんなに減らされるとは思わなかった。金額にすると三十万円そこそこ。
数ヶ月の結果としては低すぎる金額だ。正直、何度かの上京と缶詰だけでほぼ赤字。
――しかし、俺はその数字に不満はなかった。
とにかく、ともあれ三巻は出たのだ。上出来だ。敗北かもしれないけど、まあ満足だ。
一巻で切られるシリーズも多くなってきた。三巻打ち切りなら、一応話にはなる。
むしろ爽快感すらあった。どうにかギリギリ言いたい事を言って逃げ切った。そんな爽快感。
これで一勝一敗。まだ一勝一敗。しかも一敗は価値のある一敗だ。ほぼ勝ちみたいなもの。
今回はまあいい。書きたい事を書いて逃げた。今回はこれでいい。で、本気は次で出せばいい。
第三シリーズは売れるものを書いて、そして第一シリーズ超えをしよう。
第二シリーズは、まあ楽しい小休止だった。第三シリーズはエース本来の力を出し、本来の座に座りなおそう。
そう考え、俺は担当にメールを出した。
「第三シリーズの企画、どうしましょうか?」
そして、ここから世界が変わり始める。悪い方向へ。
第二シリーズが終わり、俺は再び「シリーズ企画中」の身になった。
そして再び待遇が変わった。以前とは比べ物にならないくらい、いきなり滑り落ちた。
前の経験である程度の覚悟はしていた。その覚悟なんて話にならなかった。それはもう突然滑り落ちた。
まず、向こうから提案される企画がなくなった。『次はこんな作品を』という希望がなくなった。
『次はこういう企画で行きましょう』から、『いいのを考えてどんどん出してください』になった。
前回のお題は「ヒロインと主人公が殺し合う話」だった。そして、次のお題は「自由」だ。
俺は自分の力だけで企画を作り、そしてそれを担当に見せて決済を貰う立場になった。
思いついた新企画のアイデアを、メールで次々と送っていく。
『世界滅亡したけど現実逃避して日常系』『異世界から少女が来る話』『女の子を武器にして戦う話』……他、色々。
十個単位で出せと言われていた。十個が思いつくたびに次々と出していく。そして全てが却下。
今までは原稿を送れば即座に「受け取りました」があった。そして数日後には返事があった。
第一シリーズ執筆中は文句なくそうだった。第二シリーズ企画中もまあまあそうだった。
第二シリーズ執筆中もそうだった。完結巻のあとがきを送付するまでは、確かにそうだった。
それが終わったら、担当の返事はいきなり遅くなった。そして猛烈に悪くなった。
「受け取りました」のメールすら来ない。「全て却下」の返事は三週間後。そんな感じ。
俺は勘違いしていたのだ。俺は、自分の戦歴を一勝一敗だと思っていた。
しかし、担当にとってはそうではなかった。担当にとって俺は「敗北した作家」だった。
期待のシリーズを立ち上げたものの、大して売れずに敗北した作家。俺の評価はそれだった。
敗北した。シリーズをコカした。それが今の全てだ。『過去に一勝した』のは、あくまで参考事実のひとつ。
敗北したんだから、一からやり直し。行列の一番後ろに並んでまたそこからやり直し。
やっと理解した。俺は既にエースではないのだ。エースではなかったのだ。
滑り落ち、そしてただの「新企画をコかしたラノベ作家(シリーズ執筆中)」という立場になっていた。
しかしシリーズ執筆中故にある程度優先され、だから気付けなかったのだ。
そして最終巻が7400部に終わり、今の立場になった。俺は、やっとそれを理解した。
理解したからと言って、担当からの放置状態を安穏と過ごせるかと言うと勿論そんな事はなかった。
三週間は遠い。自分の作家としての力を込めた提案をして、そして待たされる三週間は本当に長いのだ。
送る。来ない。まだ来ない。ひょっとして問題外だったのか? 来ない。日々悶々と考える。
俺にとって、ラノベ業界との繋がりは担当しかない。
俺の「プロ作家」を保障してくれるのは、そういえば担当しかいなかった。
受賞してプロ作家になって、俺の世界は一変した。
日々は興奮と快感と称賛と充実に満ち、プライドと読者を手に入れた。世界を手に入れた。
そして考えてみれば、それら全ては担当一人に依るものだった。
俺の全てはラノベ作家であり、ラノベ作家としての俺は全て担当の胸先三寸、掌の上だった。
担当が掌を返せば、俺の全てがなくなってしまう。俺はそんな存在だったのだ。
全部兄目化してるじゃねーかよって今なら突っ込めるよね(´・ω・`)。
プロ作家として何もできない。プロ作家ですらないかもしれない果てのない待機期間。
その末に、やっと返事が来る。『全部却下』という返事。
そしてまた考える。たぶんダメに決まっている企画を、俺の新作の卵をまた作る。また待つ。却下。
ふと気付けば、ラノベ業界の景色が変わっていた。
新しい参入レーベルもなくなり、新人賞受賞者たちはほぼ売れなくなっていた。
なにより──脱落者が出始めた。
最初の大量採用ラノベ作家の中から、続く大量受賞者の中から、消えゆく者が発生し始めた。
考えてみれば当たり前だった。当然の物理限界が、必然としてやってきた。
毎月新人がデビューし、その新人達は全員が続々と続刊を出していく。するとどうなる。満員になる。
満員になった。でも入ってくる。誰かが落ちる。誰かが入ったら誰かが消える。消えないなら誰も入れない。
かつて無限に広がると思われていた新大陸。その限界が、徐々に明らかになっていった。
この限られた土地が全てだ。俺達の、そしてこれから年々延々やって来る入植者全員の食い扶持だ。
「プロ作家の愚痴スレ」に書きこまれる内容が、変わっていった。
たった数年前は「編集からの返事おっそ! 再来月発売なのにヤッベ!」だった。
それが変わった。「返事おっそ!」は担当による長期間放置だったし、「ヤッベ!」は本当に危険だった。
皆がやっと気付き、そしてそれはネットによって一般の読者にも広がって行った。
世間がやっと気付き始めた。「ラノベ作家の本当」が、ネットを通して徐々に広がって行った。
本物かどうかは知らんけどハルヒの作者も来てたし
創文板はプロの人がちょくちょく来てたみたいだよ
文体と書いている内容からこの人ひょっとしてって人と遭遇してる
ネットで調べものしてた時に掲示板でもしかしたらって人と遭遇した事もあるし
そうなのか
俺がハルヒの人?を見たのはここだったけどね
ワナビの頃はそう思っていた。かつてのワナビスレではそう信じられていた。プロスレですらそうだった。
作家は自分の魂の叫びのままに自由に書き、そしてその全てが本にしてもらえると思っていた。
「創作の苦悩」という言葉は知っていた。言葉だけは知っていた。
そして、「苦悩」はロマンチックなものだと思っていた。作家に許可された特権だとすら思っていた。
作品世界が応えてくれないとか、キャラが動かないとか、まあそういう類の。それが「苦悩」だと思っていた。
漫画にあるような「先生! 印刷所がカンカンですよ!」「アイデアが出ない!」な絵図しか想像しなかった。
その末に、何か『創作の深淵』的な境地に達して書けなくなる奴もいるんだろう。
そんな訳はなかった。
ただ企画が通らないだけだ。企画が通らないから書けない。それだけだ。深淵もクソもない。
気付いた。分かった。しかし、だからと言ってどうしようもない。
何に気付いた所で、何がどう分かった所で、企画が通る訳ではない。
やる事は、やれる事は同じだ。企画を出す。待つ。却下。それだけ。
それでもやっと、企画は通った。
第二シリーズ完結巻出版がとうの過去になり、冬を過ぎ、年を越し、春を迎え、そしてやっと企画が通った。
そこまでやって、やっと企画だけが通った。第三シリーズの方向性が、やっと決まった。
「自称『リア充を目指す主人公』が、自身リア充化計画の為に部活を作り女の子を集めていく
集まった女の子(開始時点で全員の好感度マックス状態)と共に、リア充になる為の活動を日々行う」
そっくりそのままだ。何にそっくりかは言わなくてもわかりそうだが一応言う。
当時売れまくっていた「ぼくは友達が少ない」の、そっくりコピー(超劣化)だ。
当たり前だ。俺は担当を通す為だけに提案し、担当は会議を通す為だけに採用した。その結果はこうなる。
「有名な誰かの本を真似しても無為。読者はその『誰かの本』を読めばそれで事足りている」
「今売れているものを真似しても無意味。本になる頃にはブームが過ぎ去っている」
ワナビ向けの創作技法の本には必ず書いてあるだろう。言われなくても誰でもわかる明白な事実だ。
でも作家は今売れている作品にそっくりな企画を出すし、担当も今売れている作品の類似企画を採用する。
誰もがより良い道を模索している筈なのに、誰もが納得しない結果へと走っていく。
なんでこうなるのかは分からない。誰かがどうにかすれば止まるだろう。でも俺はその誰かにはなれなかった。
企画が通った。それが全てだ。この企画を元に文字を書けば本になる。それが全てだ。
正直なところ、止めようかとも思った。切実に。止めてしまえば本文を書かなくて済む。
第一シリーズは成功。第二シリーズは打ち切り。それで引退。別に恥じ入るべき戦歴でもない。
まあまあ面白かったけど、商売向きの作家じゃなかったね。惜しい。そのくらいの評価はつくかもしれない。
むしろ、それが俺につく最大級の評価かもしれない。これ以上はないのかもしれない。
でも、止めなかった。止めるか止めないかの選択肢は「止めない」とは選べなかった。
俺は第二シリーズ完結以降も、プロ作家として作家仲間と遊んでいた。
現役作家として、現役作家のつもりで『作家仲間』に混じっていた。
あの日々は……時にワナビに創作技法を伝授までしていた日々は、現役作家という前提の日々だったのだ。
ある作家がその時プロかどうかは、結果でしかわからない。未来にならないと分からない。
その後その作家が本を出せば「出版の準備中だった現役プロ」だったという事だし、
その後本を出せなければ「出版とは無関係の作業をやっていた元プロ」だったという事だ。
プロ作家でもない癖に、プロ作家に混じっていた事になる。プロのつもりで高説を語っていた事になる。
偉そうなことを言っておいて、同列のつもりで語っていて、実は既に脱落していた。それはあまりにも無様だ。
まだ書く。まだ本を出す。俺はまだプロ作家だ。どんな形でもいいから本を出す。
そして決心した。これが最後の一シリーズだ。このシリーズ最終巻のあとがきで、俺は引退宣言をする。
もうあんな中途半端な事はしない。仲間と遊ぶのはその引退宣言の日までだ。その日でキッチリ卒業する。
卒業のあとがきの為に、俺はこの本文を書く。あとがき数ページの為に、本文すべてを書く。
この決心をした理由は、俺の私生活にもあった。
ちょうどこの時期、俺の身に僥倖が起きていた。
見合いが成功した。婚約破棄されてから一応形式的に続けていた見合い。それがここでいきなり成功した。
数年間連戦連敗でほとんど作業と化していたそれが、いきなり一人の人と成功した。
俺の返事によっては婚約を考えてもいい。そんな状況まで一気に進んだ。
決断だった。俺の年齢は三十代中盤に差し掛かっていた。ここで断ればこのまま生涯独身決定だろう。
作家としての第三シリーズの企画と同時期に、俺の人生にまた一つの分岐が訪れた。結婚か。生涯独身か。
そして俺は、結婚を選択した。
生涯独身が不幸かどうかは分からない。しかし、俺がこのまま生涯独身なら少なくとも老後にこう思うだろう。
『あの時ラノベ作家にさえならなければ、俺は婚約破棄されなかったのに。結婚出来ていたのに』
『あの時投稿さえしなければ、受賞さえしなければ、俺にも子や孫がいた筈なのに』
それだけは、絶対に避けなければならない。受賞した事を後悔する事態だけは、避けなければならない。
だから俺は婚約した。俺はこの時点で、ただ俺が後悔しない為だけに婚約した。
ラブコメなら主人公に殴られる悪役の立場だろう。でも俺はもう三十路で、そんな余裕はなかった。
ラノベ作家は俺の人生の全てだった。そして、俺はラノベ作家から人生を取り返す事にした。
そんな俺の私生活など、担当には勿論関係ない。執筆許可が出た。
ガラパゴスの生物を更につぎはぎにしたキメラのようなヒロインが三人揃った所で、執筆許可が出た。
ゲロを吐くかと思った。実際、執筆中はわりと吐いた。
それが一気に身バレして窮地に追い込まれた人気ラノベ作家(?)だっておるんや(´・ω・`)。
支倉凍砂とかな(´・ω・`)。
本来ならわっち完結まで兄目化されるはずだったけど、やらかした今となっては続編不能とゆう(´・ω・`)。
せっかく原作完結しとるのにもったいない(´・ω・`)。
結局「書く」「書かない」しか選択肢はない。そして「書かない」は選べない。なら「書く」しかない。
執筆環境は酷かった。机に座る。一時間自己嫌悪をして一時間現実逃避をしてやっと一時間書く。そんな感じ。
キャラが動くも何もない。そもそもこいつらが何者なのか何をしたいのかさっぱり分からない。
分かる筈もない。企画の段階で分からなくなっているのだから執筆中に分かる訳がない。
なんでこんな事をしているのだろう。なんでこんな原稿を書くハメになったのだろう。
俺は天才だったのに。エースだったのに。期待のルーキーだったのに。アニメ化目前だったのに。
十五年の雌伏を乗り越え、爆発的デビューを飾った麒麟児だったのに。どこで間違ったのだろう。
最初から間違っていたのだ。俺は天才じゃない。天才は十五年間もワナビをやらない。
天才はたかが新人賞に十五年もかけない。たかが最初の関門に大騒ぎしない。
中高は当然クラスの中心にいていい大学に通って彼女がいてなんならもう社会で一角の成果を上げていて、
そして例えばハルヒを読んでふと思い立って片手間にラノベを書いたらそれで受賞。そんな連中。
連中は、新人賞くらい『ああ、そんなのが最初にあったっけ?』くらいの勢いで突破してしまうのだ。
連中にとっては、プロの舞台もおそらくこれまでと同じなのだろう。
傾向を掴み、分析し、成功の法則を考える。実践する。成功する。それだけだ。シンプルで最強の必殺技。
俺は出来なかった。やろうともしなかった。今さら勉強する事なんか出来やしない。
俺にあったのは勢いと情熱だけだった。それだけしかなかった。
編集者に渡す正式な企画書の書き方も知らない。会議でプレゼンできるパワポの作り方も分からない。
漫画に出てくるような「勢いで全てを解決する天才作家」のつもりで、なんの研鑽もしてこなかった。
そんな風に現実逃避し、そしてやっと書き始める。ただ書く。空白を埋める。それだけだ。
夜には空白を文字で埋める作業を続け、そして昼には結婚の話を進めていった。
一回目の失敗は繰り返さない。すぐに入籍と結婚式の日取りを決めた。来年の春に結婚だ。
むしろ安心した。今後の具体的な計画が出来た。
結婚まであと数カ月。とにかくさっさとこの一巻を出し、そして結婚式までに二巻の原稿を書いておく。
その二巻で終わりだ。一巻がどれだけ売れようが、それで完結。終わらせる。
二巻のあとがきに「結婚しました。皆ありがとう。これで引退します」と書く。それでハッピーエンドだ。
この二巻完結前提の計画は、もちろん担当には秘密にしていた。
秘密のハッピーエンド計画。その希望だけ頼りに、俺はついに本文を書きあげた。一巻分の文字を全て埋めた。
完成した原稿を送り、そして打ち合わせの上京をした。制限時間がある。早く済ませなければならない。
打ち合わせの場で、担当は唸ってしばらく動かなかった。
そりゃそうだろう。正直どこから手をつけていいのかもわからない。作者にすら分からん。
しかし、紛う方なく企画通りだ。そっちが編集会議で通したそのまんまの内容だ。
俺には既に悪智恵もついていた。担当はサラリーマンだ。会議で通ったものを自分の一存で没にはできない。
打合せの結果、主な変更改善点は「この場面でこのキャラがジョジョ立ち」だった。
なんで突然ジョジョ立ちなんだ。そんな質問や反論には意味はない。
それが今ラノベ業界でそこそこの鉄板ネタだからだ。それだけだ。その理由すらどうでもいい。
とにかくキャラを作中でジョジョ立ちさせれば本になる。ならやる。それだけだ。
どうせ「キレのいいジョジョ立ちをした。ゴゴゴゴ。ズギューン」とか入力する程度の手間だ。十分で終わる。
ついでに「ジョジョ立ち!イメージにぴったりです」とメールに添えておけば、通る可能性も上がるだろう。
これも当時流行の「状況説明そのまんま文章」な長いタイトルが自動的につき、そしてイラストがついた。
正直、イラストは当たりだった。そう言えば最初からイラスト運はあった。
これでいける。そう思った。これでいける。このイラストなら騙せる。
どうせ買う時点では中身なんかわかりはしないのだ。新シリーズ一巻の売り上げに内容なんて関係ない。
一巻の売り上げ要素は、企画、キャッチとあらすじ、イラスト。だいたいそれだけだ。
一巻は、またそこそこ売れるだろう。前よりは売れないだろうけど、まあそこそこに。
売れて、そして内容を見て投げ出されるだろうけどそれは関係ない。売れればその時点で勝ちだ。
そして二巻は売れないだろう。一巻の内容を読んで続刊を買う奴はきっと少ない。
構わない。というか、望む所だ。二巻が売れなくても俺は全く困らない。
一巻の原稿が完成し、そして発売日まであと二カ月。結婚式まで数カ月。
俺は全力で二巻を書き進めていった。相変わらず執筆状況は酷かったが、膨大な時間を使う事でカバーした。
結婚式の準備をしつつ、残った有給を全て使いつくす勢いで二巻を進めていった。
一巻のあとがきには第一シリーズの裏話を書いた。これも是非「俺の本」に書いておきたかった事だ。
二巻あとがきのハッピーエンドに通じる伏線を密かに含め、何食わぬ顔をして一巻あとがきを担当に渡した。
二巻の原稿が八割ほど完成した頃、第三シリーズ一巻が発売した。
書いていた完結二巻の原稿も、そして希望だったハッピーエンドのあとがきも、全て無駄になった。
全てが、突然途切れてしまった。どんなエンドにも辿り着けなかった。
結婚式は順調に終わった。俺は実家を出てアパートに引っ越し、新生活が始まった。
結婚して、生活や仕事も変わった。結婚をきっかけに受け持つ仕事が増え、勤務時間も長くなった。
生活に必要な様々な事で、自由な時間が圧倒的に少なくなった。
二巻執筆に使っていたノートと印刷原稿は焼却し、原稿データはパソコンの奥に移動した。
多分二度と開かないであろう「第三シリーズ」ファイルの奥に。
第二シリーズの時は分からなかった。全てを完結巻に詰め込んで出版できたから、気付けなかった。
体感してやっとわかった。一巻打ち切りとはこういうものだ。
書いていた物が、夢想していた物語が突然途切れる。打ち切りとはこういうものだ。
言い残した事も書きかけの物語もそのままで、俺の新生活が始まった。
結婚により、いよいよ『本業』が忙しくなった。そう言えば俺はそれを疎かにしていた。
既に三十路半ば、完全に中年だ。そろそろライトノベルを書いていられる年齢でもなくなった。
ラノベ書く事を、担当に連絡をする事をどうしても辞められなかった。
この期に及んで、まだ俺はラノベ作家であり続けたくて足掻いていた。
考えてみれば、第三シリーズは当初の目的を完全に果たした。「とにかく本を出す」という計画は完遂された。
俺は本を出した。つまりプロだ。打ち切り連絡のあの瞬間までは、確実にプロだった。これで確定した。
以前の「プロ作家でもないのにプロに混じっている」という疑いは完全に晴れた。そもそもそれが目的だった。
打ち切りだとか駄作だとかは関係ない。本が出たのだからプロだ。打ち切りも駄作も、プロにはよくある事だ。
それが最後の目的の筈だった。その他の事は、あくまでもオマケだった筈だ。
内容なんて気にしなかった。予想と予定通り、感想は芳しいものではなかった。
「第一シリーズは良かったのに。やっぱり一発屋だったんだな」という感想もついた。
それでも俺は、第三シリーズの発売は嬉しかった。本になって並んだ時に変わらず感動した。
書いている間は、もう縁を切りたいと心から思っていた。
いざそれが本になって、それを見た俺はしかし「書かなければ良かった」とは一切思わなかった。
「もう一度書きたい。今度こそ俺の言葉で俺の作品を書いて、言い残した事を言いたい」と思った。
まだ言いたい事はあった。言い残した事があった。途切れたハッピーエンドの続きを、出したくなった。
三十路半ばになって、既婚者になって、でも俺はまだゴールできなかった
ラノベもそういうのあるんかね?
「東京へ来られるなら時間を取ります。また頑張って打合せから始めましょう」と言ってくれた。
まだ俺はラノベ作家だった。担当は俺をまだラノベ作家と認めてくれていた。
第二に続き、第三も負けた。連敗だ。多分俺はもう最底辺のラノベ作家だ。文句なく行列の最後尾だ。
だが、列の最後尾になら並ばせてくれる。俺はまだラノベ作家だ。最底辺のラノベ作家だ。
なら、ラノベを書くしかない。まだ書けるのだから、書きたい。まだ本を出したい。
全盛期の本家ニュー速で流行ってた話が元になっとるで(´・ω・`)。
はがないは他にもちょいちょいニュー速ネタ拾ってたし、ラノベ作家はネラーやで(´・ω・`)。
なるほどなあ
この時期のラノベはドクロちゃんくらいしか読んでないからよく知らんけど
流石に独身の時のような風にはいかなかったが、それでも一日に一時間程度は机に向かえた。
かつての俺──有頂天だった時の俺より、圧倒的に環境も立場も悪い。
しかし、それはもう構わない。最底辺の俺にはもう続刊や新刊を急ぐ必要などない。
そう、今度は俺が「いくら遅くなってもいい」立場だ。これで相手と対等だ。
目標は五年間だ。そう思った。
今年は作家生活六年目。作家生活十年目までに、俺は第四シリーズを出す。
たとえ一巻で打ち切られようとも、全てを出しつくして出版されればそれでいい。
今度こそ悔いは残さない。悔いを残さず、全ての言葉を世に出して見せる。
六年目の俺は、そう決意した。
愚かしくも。あれだけの失敗をしておいて、まだ懲りもせずにそう決意した。
互いに中年だからもっと時間がかかると思っていた。数年くらいはかかると思っていた。
しかしそんな知識や心配や計画など完全に無視し、ごく順調に妊娠した。
妊娠中は色々と気を使った。とはいえ、狭いアパートでは家事も少なく、やることも少なかった。
一日一時間の執筆時間が半時間になる程度の影響はあったが、しかし毎日パソコンに向かう事は出来た。
忙しくなった日々の生活の中で、それでも企画を作っては担当に送る程度の時間は捻りだせた。
企画を送れば相変わらず長い長い待機時間があったが、しかしこの状況ではそれほど負担ではなかった。
妊娠中は考える事や考えなければならない事、考えても仕方ないのに考えてしまう事が多かった。
初妊娠という事で、妊婦検診のたびに不安材料が出てきた。検診へ行かなくても不安な症状が多くあった。
その不安で手いっぱいで、正直担当の返事が遅いのは気にする余裕はなかった……気にしなくて済んだ。
怪我の功名と言えば語弊があるが(妊娠は怪我ではない)、
しかし結果的に、俺は妻の妊娠のおかげで第四シリーズの企画に落ち着いて取りかかれた。
焦りや雑念などを排し、ただ一本筋の通った物語を作って行く事が出来た。
実際、焦っても仕方なかったのだ。
なにしろ俺は行列の最後尾だ。売れっ子やベテランにどんどん横入りもされているだろう。
なら、気にする事はない。気にしても仕方ない。
ただ少しずつ進む。少しずつ自分の納得できる物語、企画を作っていく。
今年中に企画が通ればいい。何なら来年中でも構わない。そして再来年に執筆して、更に次の年に出版。
それでも『五年以内』という目標は充分に達成できる。俺は最底辺ラノベ作家だ。もう時間とは無縁だ。
そんな風に新生活は過ぎていき、そして年末。
子供が無事に生まれた。散々していた心配は全て杞憂だった。健康的な子供だった。
何の因果か、それとほぼ同時に企画が通った。第四シリーズの企画が通った。
企画が通り、そして春には執筆許可が出た。
そして子供が生まれ、自由な時間が圧倒的に無くなった。
一日半時間の執筆どころではなかった。そもそも「余った時間」は基本的に存在しなくなった。
仕事以外のほぼ全ての時間が育児になった。子供がこんなに手間のかかるものだとは思わなかった。
しかし企画は既に通っていた。今更後に引ける状況ではない。
担当は「とりあえず一ヶ月後に〆切でどうでしょう」と言ってきたが、頼んで半年後にしてもらった。
企画は一年以上かかったのだから、今さら半年くらいの執筆期間は誤差だろうと思っていた。
担当は「まあいいです。半年ですね」とあっさり承諾し、そして執筆が始まった。
時間はない。だからどうにか作るしかなかった。
仕事以外の時間は全て育児で、そして育児は外せない。なら仕事から作るしかない。
俺は外出のたびに執筆セットを持ち出し、外での空いた時間を使って喫茶店で執筆した。
泊まり出張の時は時間の稼ぎ時だった。新幹線やホテルの部屋で全力で執筆した。
職場での机仕事中には流石にやらなかったが、しかし片手間でコッソリとプロットを修正するくらいはした。
考えてみれば、プロになってからの俺はいつも急いでいた。
勢い任せに突き進み、矛盾が出たら突貫で誤魔化し、とにかく作ってから辻褄を合わせる。そんな感じだった。
こうしてじっくりと設計図から注意深く作って行くのは、考えてみればワナビの頃以来だった。
かつての勢いはなくなった。しかし、初心が戻ってきた。
今書いているこの原稿が出版される。本になる。イラストがついて本屋に並ぶ。それは大した事だ。
思えばワナビの頃は「生涯で一冊を出版できればそれで大成功」と思っていた。
とにかく一冊。賞外拾い上げの最低ロット出版の大阪屋圏外でもいい。一冊出せればそれでいいと思っていた。
俺は幸福過ぎたのだ。幸福過ぎて、初心の頃の喜びを忘れていたのだ。
俺は物語を作っている。物語は本になる。それで充分じゃないか。そう思った。
そう思って、日々物語を進めていく。春が終わり、夏が来て、そして秋になった。原稿は完成した。
まあ第一シリーズには遠く及ばないとしても、第三シリーズは超えた。第二シリーズとも競える。
やはり初心に帰ったのが正しかったのだ。諦めなくて良かった。投げ出さなくて良かった。
第三シリーズはずっと辛かった。その後も辛かった。しかしそれが報われる。そう思った。
そしてこれが俺の完結編だ。たとえこの一冊で打ち切られても、それはそれで構わない。
あとがきを書こう。以前とは違う、俺の完結編としてふさわしいあとがきを添えてこの本を出そう。
でもまあ……ひょっとして、二巻も出るかもな……それも考えて文面を練らないとな……
そんな事を思いつつ、俺はまた上京の段取りをつけた。
第四シリーズ第一稿を送っての、第一回修正箇所打合せ上京だ。
ちなみに第四シリーズの内容はこんな感じ。
『超魔法とかを使ってしまう様々な異種族少女が通う高校。そこに転入した普通の高校生主人公。
主人公は異能なしのコミュ力のみで皆を「友人」にして無害化していく。最終目標はクラス全員ハーレム』
危険な魔王少女とかを主人公が「普通の学生生活」の力で懐柔し、そして次々と普通の友人にしていく。
まあ普通の企画だ。普通にどこにでもあるラノベ企画だと思う。
ひょっとしたら二巻は出るかもしれない。出たらちょっと執筆時間が厳しいが……
まあ有給もあるし、なんとかなるだろう。そう思いつつ、俺は上京した。
「主人公がちょっと弱いと思うんですよね」
主人公が弱い? そんな抽象的な事を言われたのは初めてだ。キャラが薄いんだろうか。
「いえ、キャラとかじゃなく戦闘力。バトル能力が弱いです。魔力のない普通の高校生って弱いですよね」
そりゃそうだ。そういう話なんだから。普通の高校生が、超強い少女を『普通』にしていく話だ。
「ヒロインより弱い主人公って、実は良くないんです」
実はと言われても、これはそういう企画で始まった。力では敵わない相手に、危険を冒して熱意の友情で……
「主人公を超最強のチートにして下さい。最強ヒロイン全員がかりでもまだ敵わないってくらい強く修正」
意味が分からない。根本的におかしい。企画の根本がズレている。何これ。何が起きた?
「今の読者は無双モノが好きなんです。主人公は最強無双に変更」
全ボツって事ですか? と聞けば「ボツじゃなく書き直し」という返事が返ってきただろう。
企画会議で通ったものを担当者の一存でボツにはできない。多分それは正しかった。
だから、作家側から言わなければならないのだ。「全部イチからやり直します」と。
担当は「そうですね。やり直した方が早そうですね」とあっさり肯定した。
イチから。数年前だった企画提出からやり直し。数年前まで遡って、またそこからやり直し。
全ては無駄だった。諦めなかった事は無駄だった。時間を作っての執筆も無駄だった。
イケる流れだったじゃねえか。帰りの新幹線で、ただ思った。
イイ感じに来てただろうが。もうハッピーエンドしかない流れだっただろうが。
堕落した作家が最後に初心に帰り、少しの希望を拾ってハッピーエンド。それで上手く纏まったじゃないか。
なんでこうなるんだ。こんな終わり方はあり得ない。こんな結末なんて誰が納得するんだ。
現実世界に物語なんてない。
決定した。通達された。それだけだ。
ネット小説が次々書籍化し始め、売れ筋は「最強主人公が無双」「異世界ワープ」になっていた。
俺の長い企画期間と半年の執筆期間で、主流は完全に変遷していた。
そして第四シリーズは、学園異能魔王少女リア充モノはもう完全に時代遅れだった。
それでも以前ならまだ何とかなったのかもしれない。様子見の枠埋めでどうにかなったのかもしれない。
それこそジョジョ立ちなり仮面ライダーの変身ポーズなりをキメれば、それで出版に届いたのかもしれない。
しかし、もうラノベ業界は「とりあえず試しに出版してみる」など許されない場所になっていた。
底辺作家が一昔前のプロットで原稿を書いてきた。それはもう出版できない。丸ボツにするしかない。
また勘違いだ。幾つ勘違いを正せば、俺は真人間になれるんだろう。
俺は「底辺」を、何かロマンチックなものとでも勘違いしていたようだ。
底辺とはこういうものだ。真っ先に切られる。あっさりと酷い目に合わされる。それが底辺だ。
雑草はどこにでも生えてくる。刈っても刈ってもいくらでも花を咲かせる。それを人は雑草魂と呼ぶ。
だが刈られた雑草当人にとってはそれっきりだ。魂もクソもない。花瓶の中で咲く方がいいに決まってる。
「今どきの子は学園と家とコンビニしかないから異世界なんて面倒くさがる」と断言してたのは誰だ。
その今どきの子は、その後たった数年で異世界開拓バトルフロンティアスピリッツにでも目覚めたってのか。
「今どきの子は家からも学校からも逃避し、全く関係のない異世界へ行きたがる」とでも分析するのだろう。
その分析結果で、作家は企画を練って編集会議は企画を通して営業は販売戦略を決めるのだろう。
そんな事は皆分かっているのだろう。分かっていて、でも「分析」をしてみせる。それが大人というものだ。
俺は大人じゃなかった。ラノベ作家は夢で、ラノベは自己実現の手段だった。
だからこうなったのか。いや大人だろうが子供だろうがどっちみちこうなったのだろう。
子供のまま売れる奴もいる。大人になっても売れない奴もいる。
売れた奴だけが勝利の秘訣を語る。自らの分析の確かさを語る。売れなかった奴は何も語れずただ消えるのだ。
ラノベでGTOヒロインがなぜ売れたのか。答えは簡単だった。それ以外は全て売れなかったからだ。
以前と同じ文面だ。第三シリーズが打ち切られた時と同じ文面。
以前の俺はこれを真に受けた。今の俺には真に受けられなかった。
あまりにもあっけなく、全てが終わった。
俺の完結巻は第三シリーズの一巻。あの中途半端な打ち切り作品が俺の最終巻になってしまった。
終わり方なんて選べない。華々しい引退試合なんて選ばれた者だけができる夢物語だ。
自分が終わった事にさえ気づけず歩き続け、遥かな未来でふと力尽きる。それがラノベ作家の死だ。
俺は全てを放置し、ただパソコンを閉じた。
『五年以内に一冊』と決めた、その次の年の秋だった。
五年の未来の先には何かがある筈だと思っていた。けど、そんな事はなかった。
七年目の秋に丸ボツを喰らい、そしてそれから半年間何をする気にもならなかった。
冬が来て年を越し、春が来てもパソコンの電源さえ入れなかった。
仮に何かをしたとして……また数年かけて企画を通して原稿を上げたとして、また丸ボツかもしれない。
その可能性があるというだけで、もう一から企画を進める気になどなれなかった。
燃え尽きていた。感動的なクライマックスなどはなく、ただ燃料が尽きて燃え尽きた。
そうして燃えた跡を片付けもせず放置し、半年。
半年が経った後、俺はその中から燃え残りを見つけた。
燃え残っていたのは、第四シリーズの原稿だ。とにかく最初から最後まで完成している物語の原稿。
創作意欲と情熱を燃やしつくし、そしてその結果としての完成物だけがそこに燃え残っていた。
それは燃え尽きた俺の、最後の希望だった。
だから、全部すっきり燃やしてしまおう。そう思った。まだ燃えるうちに。
最後の希望は、新人賞だった。
編集者にボツにされた原稿を他の出版社の新人賞に出し、下読みから突破していく。
無謀で場違いな挑戦だ。「最後の希望」だから当然だ。最後まで追い込まれたらもう手段は選べない。
それに……。これならカッコがつく。
「担当に丸ボツにされて終わり」より「新人賞に投稿して終わり」の方が、なんとなくカッコがつく気がする。
気のせいだ。気休めだ。だが、気が休まるのならそれで充分だった。
現実世界には物語なんてない。納得できる物語が欲しければ自分で作るしかないのだ。
久しぶりに戻った新人賞スレは、以前とは全く変わっていた。
既にラノベ作家の内情は知れ渡っていた。新人賞受賞者のその後は壊滅していた。それも周知の事実だった。
ほんの数年前に『もし受賞したら』で輝かしい未来を語り合っていた場所は、その姿をすっかり変えていた。
かつてこの場所で語り合っていたワナビ仲間。その何人かは多分デビューしたんだろう。
ひょっとしたらあの場のどれかで、互いにそうと知らず直接顔を合わせていたかもしれない。
彼らは……名も顔も知らない彼らは、今どうしているのだろう。今も書いているのだろうか。
今度、探してあったら読んでみるわ
様式を変え、そして続刊前提だった原稿の終盤を弄って一巻完結の終わり方へと変更する。
出版の為に続刊前提で書いた作品を、新人賞向けに一巻完結へと変更していく。
この一巻完結投稿作が仮にもし出版となったら、また出版向けに続刊前提へと戻す事になる。
誰がこんな事を始めたのかは知らないけど、ラノベの新人賞とはそういうものだ。
最初は辛かった。ずっと放置してあったパソコンの電源を入れ、また文章を開く。その動作からキツかった。
昔の文章を読むと、その文字列を目に入れるとそれを書いた頃の事を思い出してしまう。
これを書いていた頃の希望と情熱を、そしてそれが一瞬で無駄になったあの日の事を思い出してしまう。
そんな文章を読み返して再確認し、要所要所を書き直していく。それは正直言ってかなり辛かった。
……しかし、じきに慣れた。書いているうちに忘れた。忘れたフリくらいはできるようになった。
俺はワナビだった。そしてワナビは大抵、完成間近の作品を書いている時間はそれなりに幸せなのだ。
そんな日々で迎えた夏。担当から久々に連絡があった。
連絡内容は意外なものだった。「担当が変わる」
今の担当は配置転換でいなくなり、新しい編集者が俺を担当するという話だった。
俺は最後に今までのお礼の文章を書き、そしてそれを担当に送った。
担当はそれに返信をし、それが最後の連絡だった。
そして新しい担当。今更どうでもいい……とも思う。しかし、少しの期待がない訳ではなかった。
今の担当とはもうどんな未来もない。だから「別の人」というだけで、それは可能性だった。
新しい担当がどんな立場でどんな人かはわからない。だが「分からない」はそれだけで可能性だった。
万に一つ、一刻も早く出版実績を作りたくて焦っている新人編集かもしれない。
万に一つ、就任の挨拶代わりに手近なのを一冊出版するベテランの権力者かもしれない。
万に一つ……万に一つを期待し、俺はその新担当に連絡して会う約束を取り付けた。
数ヵ月後に東京で行われる授賞式。その前日に新担当は会ってくれる事になった。
その数ヶ月で、俺は投稿作を完成させた。「完全に完結している一冊分の原稿」を作った。
新担当との顔合わせにこれを素知らぬ顔で持参し、「実は一つ、完成原稿があります」と提出してみる。
こんな事をしていいのかどうかは分からない。前担当の顔を潰す行為なのかもしれない。
でも、大丈夫かもしれない。誰も気にしないかもしれない。引き継ぎはそんなに厳密ではないのかもしれない。
大丈夫か大丈夫でないかは二つに一つ。万に一つが二万に一つになるだけだ。大した差はない。
俺は新担当に会い、そして原稿を出して「今後ともよろしく」と挨拶した。
「私、あなたの本一冊も読んでないんですよ。で、どんな話書くつもりなんですか?」
「ラノベ以外で読んできた本とかありますか? ○○? それなんて人です? 知らないです。無名ですね」
「最近映画、見ました? ○○? え? 俺あれ大っ嫌いなんですよ。あんなの見たんですか?」
「あなた、ここ数年ずっと本を出されてないですよね? 読者はもう忘れてると思います」
新担当との初顔合わせと今後の打ち合わせは、30分程度で終わった。
新担当は俺と俺の出したものをすべてをただ否定し、そしてそれだけで終わった。
新担当は俺と友好な関係を関わるつもりはなく、むしろ積極的に嫌われようとしていた。
前任者がいなくなって形式的に引き継いだというだけで、特に何をするつもりはない。露骨だった。
引き継ぎは全くされていなかった。二つに一つのくじ引きは、まずアタリを引いたと言える。
そして万に一のくじ引きは、順当に9999のハズレを引いた。そして終わった。
それは俺にとって無限の成果で、担当への無限の恩だった。第一シリーズの存在は無限のプラスだった。
無限のプラスがあるから、その後いくらマイナスが積み重なっても最終決算はいつもプラスだった。
だから最後にお礼を言う事が出来たし、綺麗に終わる事が出来たのだ。
しかしこの新担当はマイナスからのスタートだ。この後も会う度にマイナスが積みあがっていくだろう。
このまま付き合い続ければ俺はマイナスに捕らわれ、じきにそれをそのまま外へと出してしまうだろう。
もう既に珍しくもない「作家が担当への不満をネットで大暴露」。その一角に名を連ねることになるだろう。
そうなったら俺は「第一シリーズの作者」ではなく「出版社と揉めた作家」として記録が残る事になる。
だから、ここで辞めよう。そう思った。この人との付き合いは、出版社との付き合いはここで辞めだ。
授賞式は、折角だから参加した。久しぶりに旧友に会った。
新人達にも会った。受賞者だけではなくネットからの拾い上げ作家もたくさん来ていた。
いわゆる「なろう作家」だ。授賞式に来るくらいだから、勿論彼は順調だった。
なろうで大人気。編集者に拾われて出版され絶好調に売れて続刊続々。「彼」は、そんな感じだった。
彼は言った。「こんなに楽でいいんですか? 実は一番チートな職ってラノベ作家なんじゃないですか?」
確かにチート職だ。チートみたいな職だった。過去形だ。俺も最初のうちはそうだった。
家でただパソコンに向かうだけで本になり先生と呼ばれ少なくない金が入る。こんな職は確かに他にない。
彼にとっては、それが今なのだろう。若き昇り竜が「ネット書籍化」という新大陸を発見したのだろう。
新大陸……彼にとっては、今この時が新大陸発見の瞬間、輝かしい歴史の最初の一歩なのだろう。
あるいは開拓者か。「ネット小説」という近代兵器を振るって原住民を追い払う、新鋭の入植者。
ひょっとしたら、彼はこれから「なろう作家だけど質問ある?」てなスレを立てるのかもしれない。
最初から、新大陸なんてなかったのかもしれない。
かつて「プロ作家の愚痴スレ」で、ベテランたちが寡黙だった理由がわかった。
今はさぞ明るくて熱いだろう。燃えているのはお前自身だ。燃え尽きてしまえばその先にはきっと何もない。
後輩にそんな事を言って、一体何になるのか。
嫉妬に駆られた老害の妄言としか取られないだろうし、実際それは嫉妬でしかないだろう。
第一……もしそいつが今後そのまま輝かしい未来を手に入れたら、俺がカッコ悪いだけじゃないか。
だから、黙るしかないのだ。そうなればいいな。応援してる。そう言ってただ去るしかないのだ。
あの世代のラノベの書き方となろうの書き方は全く違うから
なろうに来なよ
と言ってみる
かつてと同じように穴をあけて紐に綴じ、梗概をつけて出した。
ペンネームは変えた。途中選考で読者にバレないように、出版社に出がらしのプロだとバレないように。
○九年目
結果は二次落ちだった。特に失望はなかった。一次を越えられただけで上出来だ。
特に何の反省もなく、次の出版社新人賞に原稿を即座にそのまま使い回す。既に印刷封入まで出来ていた。
そういえば、十年前は落選作の使い回しはそれほど一般的なものじゃなかった。
確かMFが途中落選作品のタイトルまで発表し始め、そしてその後それが他で受賞したのが切欠だったか。
落選後の使い回しは禁止ではないとワナビに知れ渡り、それから誰も彼も使い回すようになったんだっけ。
そんな曖昧な記憶(正しいかどうかは知らない)を思い出しながら、次々と使い回していく。
〆切が近い所から封筒を作り、落選発表が出される度に次々と郵送していく。
そんな九年目だったが、少しの事件がない訳ではなかった。
新担当から、突然連絡があった。旧担当に教えていた携帯電話ではなく、実家の電話に連絡があった。
「今、作家の皆さまから企画を集めてるんですよ。近く、東京に来る予定とかないですか?」
いかにも『場合によっては出版についての話をしてもいいよ』という感じで、上京誘いの話が始まった。
俺は「時間があったら今度の授賞式に行くかもしれません」と返事した。つまり、完全に断った。
もうこの人とは付き合わないと決めていた。少しアメをぶら下げられても、その決意は別に変らなかった。
多分ノルマの形式的な質問だったのだろうが、俺の側から断ってやった。意味はなかったが少しスッキリした。
新担当は「そうですかまた機会があったら」とあっさり引き下がり、そして続きの話をした。
「ところで、ウチも電子書籍を始めます。第一シリーズを無料公開したいんですけど考えてもらえませんか?」
どう考えてもこっちが本命だ。さっきのは本当に撒き餌だったのだろう。
俺は二つ返事で「いいですよ自由に」と答えた。考えるもくそもない好きにすればいい。
今更何の権利を持っていても仕方ない。それで第一シリーズの読者が一人か二人でも増えるんなら望む所だ。
新担当からの連絡は、後にも先にもこれっきりだった。結局どこにどう無料公開されたのかは今も分からない。
投稿はどんどん進んでいった。全てが一次か二次落ちだった。
一次通過は少し嬉しかった。その嬉しさは「最後の希望」が燃えていく熱と光だ。
たまに評価シートが来たが、次作どころか書き直し修正すらしなかったので全く無意味だった。
投稿を続けながら、作家生活の後片付けを徐々に進めていった。
実家に置きっぱなしだった大量の資料や参考文献を、少しずつ整理していく。
受賞の年に店員の目を気にしつつ買った、中高生オシャレ私服雑誌一年分。
第二シリーズ目企画中に大量購入し読破した、当時売れ筋ラノベ大量。
コミケで挨拶回りをして購入した、知人や挿絵イラストレーターの同人誌。
ネットで「やる夫がラノベ作家になるようです」を見て購入した、執筆用辞書数冊。
それらを処分していく。雑誌と同人誌はゴミの日に出し、売れるものはブックオフに持っていく。
自分の本は大量にあった。第一シリーズと第二シリーズはそれぞれ勢い余って各二十冊ずつ買った。
第三シリーズは……実は、売れ行きが悪いと聞いて百冊近く自腹購入していた(前述通り、甲斐はなかった)
第一と第二はそのまま収納ケースに仕舞い、第三はブックオフに行くたびに二冊ずつ混ぜて売った。
写真は全てパソコンに移してUSBメモリに保存し、ツイッターの過去カキコは全て消した。
全ては収納ケース一箱に収まった。それが俺の成果の全てだった。
最後の新人賞に落選した。「最後の希望」まで、完全に燃え落ちた。
既に俺は四十路間近になり、二人目の子どもが生まれていた。
そんな風に、俺の作家生活は終わった。
それからまた数年が経過した。子供は大きくなり、そして俺は更にオッサンになった。
もうオタ業界に関わる機会もなくなった。今のラノベ業界がどうなっているのかは分からない。
旧友たちはどうなっているのか。今の売れ筋は何か。なろう作家の「彼」は、その後どうなったのか。
調べればすぐにわかる話だが、それはもう俺と無関係の話だ。
俺の作品と記憶の全てが入った収納箱は、まだ実家に置きっぱなしになっている。
そこにある物語の全ては、まだ今になっても思い出せる。特に第一シリーズ。有頂天の頃の話だ。
それは俺の最高傑作だったと今も思える。有頂天の俺が、雲を掴んだ物語だった。過去の栄光だ。
過去の栄光。若い頃の俺なら鼻で笑っただろう、オッサンの華やかな昔話だ。
過去の選択肢を考える時もある。
もしあの時、もし第二シリーズでA社に移籍していたら。もし第三シリーズで妥協せず企画していたら。
もし第四シリーズを一ヶ月で書けていたら。もし新担当と縁を切らずに縋り付いていれば。
そのどれかの未来では、ひょっとしてまだ俺は作家をやっていたのかもしれない。
だが今こうして自分の現状を考えてみると、やはり総括は「現世に帰ってこれて良かった」になる。
勢い余って会社を辞めるとか上京とかしなくてよかった。最終的にはやはりそういう結論で終わる。
もしもう少しラノベ作家生命が伸びていたら、俺は今ここにこうしていないだろう。
サンプルが少なすぎただけ。平均年齢が低く結婚年代でなかっただけ。種を明かしてみるとそんなのばかりだ。
結婚する奴は普通に結婚する。しない奴は普通にしない。それだけだ。何もかも普通だ。
俺の作家生活は、一瞬の絶頂とそれで勘違いした末の七転八倒と最後は見苦しい損切り終了だった。
一生に一度の奇跡の投稿作でギリギリ受賞し、その勢いで自分と業界を大いに勘違いさせて第一シリーズ完結。
第二シリーズ二巻でメッキが剥がれ始めるが打ち切り超展開でどうにか誤魔化して逃げ切り。
そして完全に剥がれたワナビ地金で第三シリーズ挑戦。撃沈。そんな感じだろう。
辛いことはいっぱいあった。人に迷惑をかけまくった。作家の矜持を汚す事をやり過ぎた。
でも人の記憶というのは便利なもので、時が経つと良かった事しか思い出せなくなる。
一纏めで「辛い事もあったけど、楽しかった作家生活」。最近は、そう認識できるようになってきた。
俺はラノベ業界という異世界でそこそこ活躍し、そして現世に帰ってきた。そう錯覚できるようになってきた。
だからこの文章を書いた。
その十年間が、俺の物語だった。
皆ありがとう
やっと終わった
お話ししよーぜ
ほんと人生は面白いな
おすすめサイト最新記事一覧
コメント
1.名無しAtoZ:2018年10月05日 21:43 ▽このコメントに返信
流石に長いんだけど読むに値する文章力ありそう?
2.名無しAtoZ:2018年10月05日 21:52 ▽このコメントに返信
作家とは思えない酷い文章やなw
夢破れたワナビが創ったネタってトコか
3.あ:2018年10月05日 21:55 ▽このコメントに返信
読もうと思ったがハルヒあたりでやめた。
これが作家の文章か?
4.名無しAtoZ:2018年10月05日 21:56 ▽このコメントに返信
あらかた事実なんだろうけど文章力や構成力からして三流だったことはすぐわかるな
5.名無しAtoZ:2018年10月05日 21:57 ▽このコメントに返信
まあ、誰しもが成功者なわけないのだから、これはこうなるわな。
一時的にでも夢を叶え、こういう形で着地してるだけ、他人から見れば幸せなほうだったと思うよ。
6.名無しAtoZ:2018年10月05日 22:01 ▽このコメントに返信
正直読みにくい
7.:2018年10月05日 22:10 ▽このコメントに返信
文章がくどくて三レス目くらいから読む気なくした。売れない作家の僻みだろ。
8.あ:2018年10月05日 22:11 ▽このコメントに返信
一昔前の自分語りスレと同じような文体だから懐かしかったよ
風俗行ったら人生変わったとか、ゲーセンで会った不思議な子の話とか
あっちは創作だったけど
9.名無しAtoZ:2018年10月05日 22:14 ▽このコメントに返信
無いと思う
無駄に長い
10.名無しAtoZ:2018年10月05日 22:16 ▽このコメントに返信
駄目だ、読みづらい
そりゃ続かないわな
11.名無しAtoZ:2018年10月05日 22:34 ▽このコメントに返信
普段は長文ウザイのコメントがウザイと思うタイプだけど、これは長すぎる
ましてや作家だったのなら、ある程度は文章を簡潔にまとめる能力がないとね
12.名無しAtoZ:2018年10月05日 22:36 ▽このコメントに返信
無い
13.名無し隊員さん:2018年10月05日 22:38 ▽このコメントに返信
読みづれぇ。作家の文章とは思えん。ストーリーとかの前に、つるつる読める文章書けないとね
14.名無し:2018年10月05日 22:44 ▽このコメントに返信
ダラダラ意味無い文書き連ねてる辺り、作家になった夢でも見てただけのニートだろコレ。語彙も貧弱、構成力も無し、要点もあやふや、馬鹿なのかな?
15.名無し:2018年10月05日 22:52 ▽このコメントに返信
こいつは冬樹忍だな
書いてあるように、俺妹時代にちょろっと売れた有象無象の1人だ
昔はこーゆー分かりづらい文体が受けたが、今見ると読み辛いなw
引退して正解だよ確かに
16. :2018年10月05日 22:54 ▽このコメントに返信
文章がクドい
リアルに昔のラノベ臭い
でも書いてあることは面白かった
もしもこれが松なら松で上手い松だったと思う
17.あほくさ:2018年10月05日 22:58 ▽このコメントに返信
本当に作家の書く文書か?と疑うほど引き込まれる箇所が一切なく、かつ読みにくいうえにどうでもいい。
最高に時間を無駄にした。途中で読むのやめたけどな
18.名無しさん:2018年10月05日 23:05 ▽このコメントに返信
冬木忍って人のwiki見たらほんとにそんな感じだった
19.名無しさん:2018年10月05日 23:18 ▽このコメントに返信
文章は普通に読みやすいと思ったけどなあ
20.名無しAtoZ:2018年10月05日 23:20 ▽このコメントに返信
読みづらすぎる
いまのラノベ業界じゃ全く通用しないだろうし早めに辞めてよかったな
21.名無しAtoZ:2018年10月05日 23:33 ▽このコメントに返信
たまなま面白かったよ
22.名無し:2018年10月05日 23:34 ▽このコメントに返信
全部読んでないけど、とりあえず西野かつみはかのこん新刊出してくれ
23.ななし:2018年10月05日 23:38 ▽このコメントに返信
要領を得ず一方的に書きたいことを書いてるだけ
相手に分かりやすく伝えるって考えが欠落してる
そりゃ売れんわ
売れたこと、調子に乗って失敗したこと、今がどうなのかを簡潔に書いてあとは質問に答えるべきだった
24.:2018年10月05日 23:40 ▽このコメントに返信
最初の数スレと最後のほうだけ読んだ。
読みにくいんだよツルッパゲ!
25.上から目線ははっぴいにゅうにゃあだけ:2018年10月05日 23:52 ▽このコメントに返信
俺はすばらしい!理解出来ない世間が悪いって感情がだだ漏れ(笑)






































































![[物語]シリーズセカンドシーズン 戦場ヶ原ひたぎ -恋物語- (1/8スケール PVC塗装済み完成品)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41sQMkh222L._AA440_CR150,30,185,330_.jpg)